『向いてない』は勘違い?視野を広げる企業研究のコツ
皆さん、こんにちは!「あおもりHRラボ」です。
前回の記事では、インターンで感じた「なんか違うな」という違和感の正体を突き止め、それを「自分だけの就活の軸」に変える方法を解説しました。ワークに取り組んでみて、改めて自分の価値観に気づいた人もいるのではないでしょうか。
さて、その「就活の軸」が明確になったら、次のステップは企業研究です。
でも、こんな風に思っていませんか?
「インターンに参加したA社は向いてないとわかったから、もうB社とC社しか見ない」
「やっぱりあの業界は自分には合わないから、もう違う業界に絞ろう…」
ちょっと待ってください!
たった一つの経験だけで、可能性を閉ざしてしまうのはもったいない。
もしかしたら、その「向いてない」という感覚は、実はただの「勘違い」かもしれません。
一つの会社のインターンで体験できることは、その業界や職種のごく一部にすぎません。
A社が合わなかったとしても、同じ業界のD社やE社なら、あなたの価値観とぴったり合う可能性があります。
今回の記事では、インターンで「向いてない」と感じた経験を、新たな企業との出会いに変えるための「視野を広げる企業研究のコツ」を、具体的な方法を交えながら解説します。
1. 「点」ではなく「線」で捉える企業研究
企業研究というと、個別の会社(点)をひたすら調べることだと思っていませんか?
しかし、本当の企業研究は、個別の会社を調べるだけでなく、業界全体や社会とのつながり(線)を理解することにあります。
インターンシップは、その「線」の一部を覗き見するチャンスです。
そこで感じた「違和感」は、あなたがその業界の「ある特定の点」と合わなかったというサインにすぎません。
例えば、「IT業界のインターンに参加して、とにかく成果主義で合わないと感じた」とします。
この時、多くの人は「IT業界は向いていない」と判断してしまいます。
しかし、IT業界の中にも、チームワークを重視する会社、個人のペースを尊重する会社、社会貢献をミッションに掲げる会社など、様々な企業が存在します。
大事なのは、「なぜ、その会社が成果主義だったのか?」という背景まで深く考えることです。
- 会社のビジネスモデルは?
- どんなフェーズの会社だった?
- どんな人が活躍していた?
この問いかけを通じて、あなたは「IT業界そのものが向いていないのではなく、〇〇な特徴を持つ企業が合わない」という、より具体的な発見をすることができます。
2. 視野を広げる!企業研究の具体的なステップ
インターンで感じた「違和感」を新たな可能性に変えるために、以下の3つのステップで企業研究を進めてみましょう。
STEP1:違和感を「キーワード」に変換する
前回の記事で言語化した「違和感から生まれた就活の軸(譲れない条件)」を、企業検索で使える具体的なキーワードに変換します。
【例】
- 譲れない条件: 「風通しの良い環境で、チームワークを重視したい」
- キーワード:
- 「チームビルディング」
- 「心理的安全性」
- 「1on1制度」
- 「社員交流」
- 「ワークショップ」
- 「風通しの良い」
これらのキーワードを、企業の採用ページやブログ記事、プレスリリースなどで検索してみましょう。
STEP2:業界を「タテ・ヨコ」で広げる
多くの学生は、一つの業界をタテに(その業界内の競合他社を)見て終わりがちです。しかし、視野を広げるためには、業界を「タテ」だけでなく「ヨコ」にも広げることが大切です。
- タテ(業界内を深掘り):
- 同業他社: インターンに参加した企業と同じ業界の、規模や設立年が異なる企業を調べてみましょう。同じ業界でも、企業文化は全く違います。
- ビジネスモデル: 業界内で、どんなビジネスモデルの企業があるか調べてみましょう。例えば、「SaaS企業」「受託開発企業」「コンサルティング企業」など。ビジネスモデルが違えば、仕事の進め方や働き方も変わります。
- ヨコ(関連業界を探索):
- 関連する業界: インターンに参加した業界の「顧客」や「サプライヤー」にあたる業界を調べてみましょう。例えば、「IT業界」が合わなかったとしても、ITシステムを導入する「メーカー」や「商社」など、関連する業界に面白い仕事があるかもしれません。
- 職種から探す: 「〇〇職(例:マーケティング職)」というキーワードで、様々な業界の企業を調べてみましょう。同じ職種でも、業界が違えば仕事内容や求められるスキルが大きく変わります。
STEP3:企業の「人」を調べる
企業のウェブサイトや採用情報だけでは、本当の雰囲気はわかりません。
企業文化や働き方を深く知るためには、実際に働く「人」に焦点を当てて調べてみましょう。
- 社員ブログ・SNS: 多くの企業が、社員が日々の仕事や会社のイベントについて語るブログやSNSアカウントを運用しています。社員の生の声から、会社の雰囲気や人間関係を推測できます。
- OBOG訪問: 実際に働く社員に直接話を聞くことが、最も効果的な方法です。自分が感じた「違和感」について、OBOGに正直に話してみるのも良いでしょう。「〇〇な社風に違和感を感じたのですが、御社ではいかがですか?」と質問することで、あなたの価値観と企業の文化が合っているか、より深く理解できます。
ワーク:あなたの「向いてない」を分解しよう
さあ、記事を読んだら早速行動に移してみましょう!
インターンで「向いてない」と感じた経験を、以下のシートを使って分解してみてください。
【あなたの「向いてない」分析シート】
- インターンで「向いてない」と感じた企業・業界・職種を一つ選んでください。
- (例:IT業界の〇〇社)
- 1で選んだものに対して、具体的にどんな点に「向いてない」と感じましたか?
- (例:残業が当たり前の雰囲気だったこと)
- (例:個人目標の達成ばかりが評価される風土だったこと)
- 2で挙げた「向いてない」の理由について、「その逆だったらどうだろう?」と問いかけてみましょう。
- (例:残業が少ない会社なら、どうだろう?)
- (例:チームワークを重視して、みんなで目標を達成する会社なら、どうだろう?)
- 3で考えた「その逆の働き方」ができる企業や業界を、STEP2を参考に調べてみましょう。
- (例:ワークライフバランスを重視するメーカー、SaaS企業)
- (例:チーム目標を重視するコンサルティング会社)
このワークを通じて、あなたは「向いてない」と感じた経験から、あなたの本当に求める働き方や企業像を、具体的に導き出すことができます。
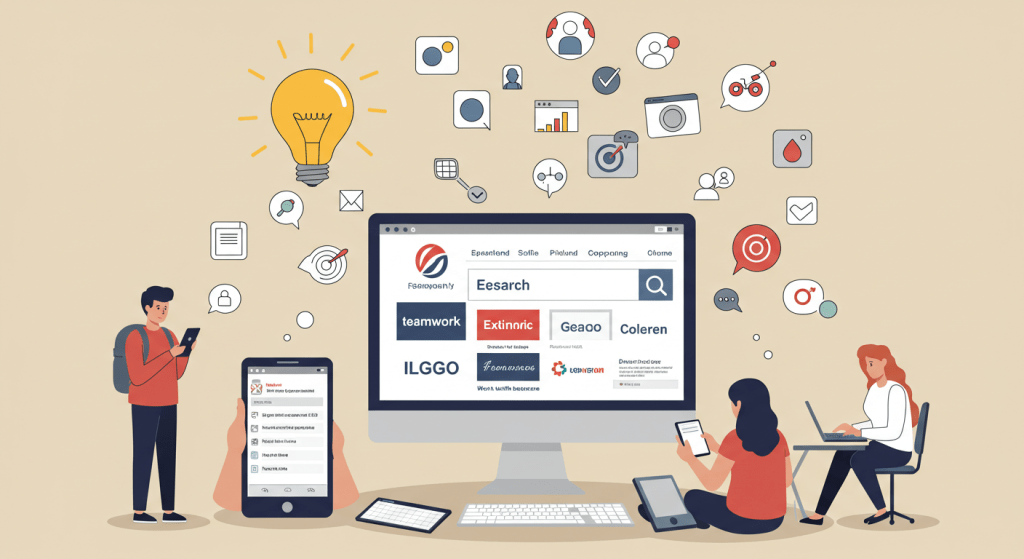
まとめ:視野を広げる勇気が、納得のキャリアを拓く
就職活動は、自分自身の「好き」や「得意」を探す旅でもありますが、それと同じくらい、自分の「苦手」や「嫌だ」を理解する旅でもあります。
インターンで感じた「向いてない」という感覚は、決してネガティブなものではありません。
それは、あなたが自分自身を深く理解するための、貴重なヒントです。
このヒントを無視せず、丁寧に紐解くことで、あなたは本当に自分が輝ける場所を見つけ出すことができます。
「向いてない」から見つかる新たな可能性
一つのインターン経験だけで、その業界や職種全体を「向いてない」と決めつけてしまうのは、あまりにももったいないことです。
それは、まるで本の一ページだけを読んで、その本全体を「面白くない」と判断してしまうのと同じ。
大切なのは、視野を広げ、多様な可能性を探求する勇気を持つことです。
もしかしたら、あなたが「向いてない」と思ったIT業界にも、あなたの価値観とぴったり合う企業があるかもしれません。
あなたが「合わない」と感じた職種も、別の業界でなら、生き生きと働くことができるかもしれません。
未来の自分を信じて
就職活動は、たくさんの選択肢と向き合う中で、時に不安になることもあるでしょう。
しかし、これまでのワークで手に入れた「自分だけのコンパス」を信じてください。
そのコンパスが示す方向を頼りに、一歩ずつ進んでいけば、必ずあなたの心が本当に納得できるキャリアに出会えるはずです。
次回予告
次回では、いよいよ面接対策の第一歩。
「自己PR」や「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)」を、ただの経験談で終わらせないための「ストーリーテリング」のコツについて解説します。
あなたの経験を、面接官の心に響く「物語」に変える方法を学びましょう。