「ペルソナ」の罠を越えて。未来を創る採用ターゲットの見極め方
人事や経営者の皆さん、こんにちは。
いよいよ10月、採用活動が本格化するこの時期に、多くの企業が頭を悩ませるのが「求める人物像」の定義ではないでしょうか。
「明るく、コミュニケーション能力が高く、自律的に動ける人」
当たり障りのない言葉でペルソナを定義し、採用活動をスタートさせていませんか?しかし、多くの企業が、そうした一般的なペルソナ設定の「罠」にはまり、期待するような人材に出会えていないという現実があります。
この連載は、一過性のノウハウではなく、人事の本質を捉え直すための羅針盤となることを目指しています。
記念すべき第1回は、採用戦略の根幹である「採用ペルソナ」をテーマに、ドラッカーの教えを紐解きながら、未来を創る人材の見極め方について、皆さんと深く考えていきたいと思います。
1. なぜ、従来の「採用ペルソナ」は機能しないのか?
多くの企業が採用活動で用いる「採用ペルソナ」は、マーケティングの世界から持ち込まれた手法です。年齢、性別、趣味、志向性といった属性を細かく設定することで、ターゲットを絞り込み、効率的な母集団形成を目指すものですが、残念ながら多くのケースで期待通りの成果が出ていません。その背景には、ペルソナ設定そのものの「本質的な限界」があります。
1.1. 属性だけでは「強み」は見えない
ドラッカーは「人は、何かをなすために、特定の強みを持っている」と述べました。(出典:『マネジメント』より)しかし、従来のペルソナ設定は、その人が持つ「強み」や「価値観」という内面的な側面に十分に着目していません。たとえば、「サークル活動でリーダーを務めた」という経験から「リーダーシップがある」と判断しても、それが組織でどう活かされるかは、その人の「価値観」と「仕事観」に深く根ざしています。属性や経験という表面的な情報だけでは、その人の本質的な強みを見抜くことはできません。
1.2. 過去の成功体験に縛られる危険性
従来の採用ペルソナは、多くの場合、社内の「既存の成功者」をモデルに作られます。しかし、これは「過去の成功体験」に縛られるという大きな危険性を孕んでいます。現代のビジネス環境はめまぐるしく変化しており、昨日までの成功モデルが、今日の正解とは限りません。過去の延長線上で採用活動を行うことは、未来の変化に対応できる組織を創る機会を自ら手放していることになります。
1.3. 画一的な人材ばかりが集まる副作用
誰もが求める「明るく、コミュニケーション能力が高い」という画一的なペルソナは、同じような人材ばかりを集めてしまうという副作用をもたらします。心理学の分野では、「人は自分と似た人間に惹かれる」という「類は友を呼ぶ」現象がよく知られています。しかし、この同質性の高いチームは、新しいアイデアやイノベーションが生まれにくいという弱点があります。多様な視点や価値観こそが、組織の成長と変革を促す原動力となるのです。
2. 未来を創る人材を見極める「強み」の視点
では、未来を創る人材を見極めるためには、どうすればいいのでしょうか?答えは、ドラッカーが説いた「強み」という視点に立ち返ることにあります。採用ペルソナの代わりに、自社の「未来」を起点に、その未来を創り出すために必要な「強み」を定義するのです。
2.1. 自社のミッション・ビジョンから「未来」を定義する
採用活動を始める前に、人事担当者が真っ先に行うべきは、自社のミッション・ビジョンを再確認することです。
「私たちは、何を目的として存在しているのか?」
「私たちは、将来どのような組織になりたいのか?」
これらの問いを掘り下げることで、組織の「未来」が明確になります。その未来を実現するために、今、どのような「強み」を持った人材が必要なのかを言語化していくのです。
2.2. 「強み」を「行動」に落とし込む
「強み」は抽象的な概念です。それを採用活動に活かすためには、「行動」に落とし込むことが重要です。
たとえば、「顧客の潜在的なニーズを引き出す力」という強みを定義したとします。これは面接でどう見極めるのでしょうか?
「過去に、相手の期待を超えた経験はありますか?」
「その時、具体的にどんな行動をしましたか?」
「なぜ、そのように行動しようと思いましたか?」
といった質問を通じて、その強みが発揮された具体的な行動や、その背景にある思考プロセスを深掘りすることで、その強みが本物かどうかを見極めることができます。
2.3. 「価値観」と「仕事観」を問う
面接で「あなたの将来の夢は?」と聞くのは、単なる興味本位ではありません。その人の「人生観」、つまり「何に幸せを感じ、何を成し遂げたいか」を知るためです。そして、その人生観と、仕事がどう結びつくのか、という「仕事観」を問うことで、その人が組織で働く上で何にモチベーションを感じるのか、自律的に動けるかという本質的な部分が見えてきます。この「価値観」こそが、その人が困難に直面したときに、自ら乗り越えるための原動力となるのです。
3. ワーク:未来を創る「強みペルソナ」の作り方
従来の採用ペルソナの代わりに、自社の未来を起点にした「強みペルソナ」を作成するワークを実践してみましょう。これは、採用に関わるすべての関係者(経営者、部門長、現場社員)を巻き込んで行うことで、より効果を発揮します。
3.1. 未来の「理想的な組織」を定義する
・3年後、自社がどのような事業環境にあるか?
・その時、理想的な組織はどんな状態か?(例:新規事業が複数立ち上がっている、部門間の連携が活発、顧客からの信頼が厚いなど)
・その組織で活躍している社員は、どのような「強み」を持っているか?
3.2. 「強み」を具体的に言語化する
ステップ1で定義した「強み」を、具体的な行動レベルまで分解して言語化しましょう。
例)
「強み」: 組織を横断する「調整力」
「行動」:
・異なる意見を持つメンバーの話を、まず最後まで聞くことができる
・対立を恐れず、本音で議論する場を自ら設定できる
・相手の立場を理解した上で、納得のいく妥協点を見つけられる
3.3. 評価項目に「強み」を組み込む
作成した「強み」と「行動」を、面接の評価項目に組み込みましょう。これにより、面接官の主観的な判断を避け、一貫性のある採用活動が可能になります。
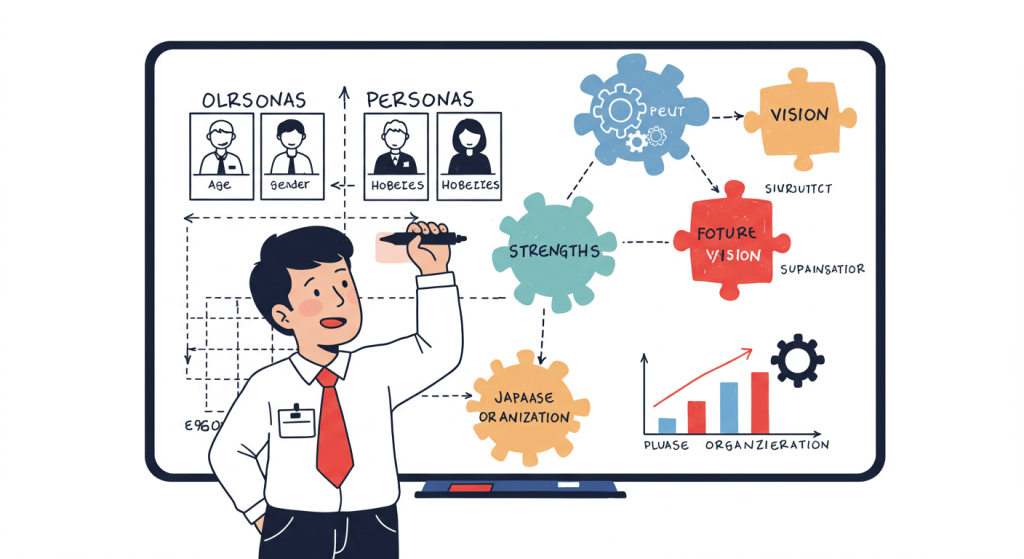
4. 採用面接を「選考」から「対話」の場へ
「強みペルソナ」を活かすためには、採用面接のあり方を根本から見直す必要があります。面接は、企業が候補者を「選考」する場ではなく、お互いの「価値観」と「強み」を確かめ合う「対話」の場へと変革していくのです。
4.1. 傾聴と共感の重要性
心理学では、「人は、自分を理解してくれると感じた相手に心を開く」ことが知られています。面接官は、一方的に質問を浴びせるのではなく、候補者の話に耳を傾け、共感を示すことで、より深い本音を引き出すことができます。これにより、候補者は安心して自分をさらけ出し、面接官は表面的な回答の裏にある、その人の本質的な価値観や強みを見抜くことができます。
4.2. 「なぜ?」を繰り返す深掘り質問
「学生時代に頑張ったことは?」という質問に対して、「サークル活動でイベントを成功させました」という答えが返ってきたとします。そこで質問を終えるのではなく、「なぜ、そのイベントを成功させたいと思ったのですか?」「困難に直面した時、なぜ諦めずに続けられたのですか?」と「なぜ?」という問いを繰り返すことで、その人の内発的な動機や価値観に迫ることができます。
4.3. 候補者のキャリア観に寄り添う
面接の最後には、「あなたのキャリアビジョンは、当社の環境でどのように実現できると思いますか?」と、候補者自身の未来に寄り添う質問を投げかけてみましょう。これは、その候補者がどれだけ自社のことを深く考えているかを知るだけでなく、「あなたのキャリアを応援したい」という企業からのメッセージとなり、候補者の入社意欲を大いに高めることにつながります。
まとめ:採用戦略は「未来の組織」を創る第一歩
今日の記事では、従来の採用ペルソナの限界を越え、自社の「未来」を起点とした「強みペルソナ」の重要性についてお話ししました。
採用は「投資」である
採用活動は、単なる欠員補充ではありません。それは、自社の未来を創るための「最も重要な投資」です。この投資の成否は、どれだけ多くの応募者を集めたかではなく、自社のビジョンに共鳴し、ともに未来を創っていける人材に出会えたかどうかで決まります。
「人」を活かすことが、組織の使命
ドラッカーは「マネジメントの使命は、人が自らの強みを発揮できるようにすることである」と説きました。(出典:『現代の経営』より)この言葉は、採用活動においても同様に当てはまります。採用の本質は、その人が持つ強みを見抜き、その強みが最大限に活かされる場所を提示することにあるのです。
採用活動を、変革の起点に
今日お伝えした「強みペルソナ」の考え方は、採用活動だけでなく、あなたの会社の組織文化を変革する第一歩にもなり得ます。採用に関わるすべての人々が、未来の組織の姿を語り合い、どのような「強み」を持つ人々と共に働きたいのかを深く考える機会となるからです。
さあ、未来を創る採用戦略を、あなたの手で始めましょう。